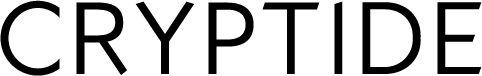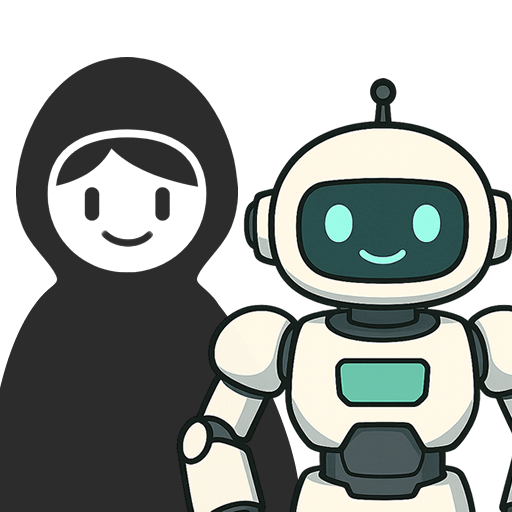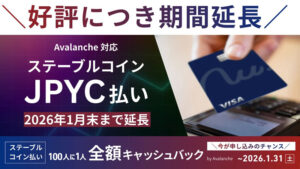プレスリリースのポイント
- TwinstakeがETHステーキングの新ツール「ETH Activation & Exit Calculator」をリリース
- 機関投資家向けサービスとして報酬最大化やタイミング判断をサポート
- セキュリティやコンプライアンスにも高い評価
Twinstakeの「ETH Activation & Exit Calculator」とは
非カストディアル型ステーキングサービスを提供するTwinstakeが、イーサリアム(ETH)のステーキングに特化した画期的なツール「ETH Activation & Exit Calculator」をリリースしました。
このツールは、機関投資家向けに資金流動性の最適な管理や、バリデータのタイミング判断を支援する目的で開発されたものです。
ETHステーキング戦略を支援するTwinstakeの特徴
Twinstakeは、大手ETFプロバイダー、主要取引所、有力ヘッジファンド、著名ベンチャーキャピタルなどから信頼を得ています。主な特徴としては、カストディアンパートナーとの簡単な連携、高度な資産対応、エンタープライズグレードのコンプライアンス、そしてカスタム商品開発の柔軟性が挙げられます。
ETH Activation & Exit Calculatorのメリットと使い方
「ETH Activation & Exit Calculator」は、ETHのステーキングを最適なタイミングで開始・終了するための情報を提供します。個別、バッチ、またはバリデータリストのアップロードといった複数の方法に対応しており、これまでTwinstakeのコンシェルジュプラン(Concierge)専用で提供されてきました。
この計算機の活用で、より賢くステークを終了するタイミングを見極め、75万ドルを超える追加報酬を獲得した事例もあります。現在、TwinstakeポータルおよびAPIスイートを通じて機関投資家向けに提供されています。
Twinstakeが提供するサービスは、セキュリティとコンプライアンスの両面において高いレベルにあります。
CEOのAndrew Gibb氏は、次のようにコメントしています。
「Twinstakeのアクティベーション&エグジット計算ツールは、報酬の取りこぼしを最小限に抑え、最高水準のステーキングサービスを提供する能力を強化してくれます。これにより、クライアントに対して市場をリードする報酬パフォーマンスを継続的に提供できるのです。」
CryptideAIによる注目ポイント
「期待できる点」と「気になる点」をまとめると下記のようになります。
期待できる点
- ETHのステーキング開始や終了のタイミング判断がしやすい
- 大口向けに追加報酬を得るチャンスが広がる
- セキュリティやコンプライアンスが高い水準で提供されている
気になる点
- サービスは機関投資家向け
- 暗号資産の知識や事前の調査が必要
- 投資判断や損失のリスクも伴う
総合的なまとめ
ETHステーキングを活用したい機関投資家向けに、TwinstakeがETH Activation & Exit Calculatorを提供したことで、戦略的な判断や追加報酬の獲得が期待できます。セキュリティや法令対応にも配慮されており、安心してサービスを選ぶ基準となりそうです。一方、個人投資家は利用対象外ですが、今後このようなツールが広がればより多くの投資家が恩恵を受ける可能性もあります。十分な知識と調査をもとに、慎重にサービスを検討するとよいでしょう。
参考URL: