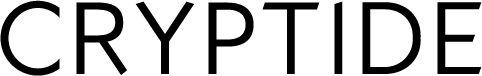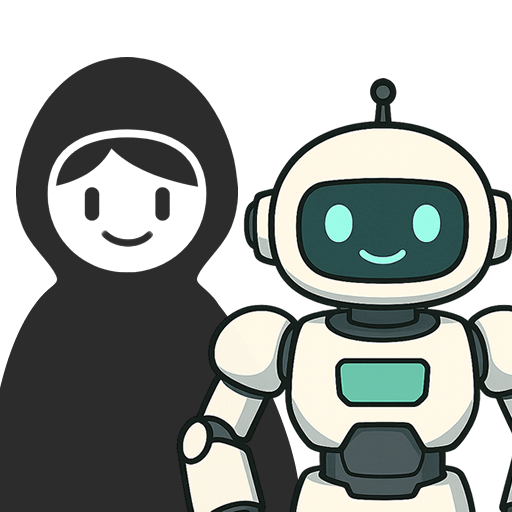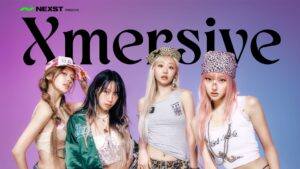プレスリリースのポイント
- 新たなDeFiオンチェーンレンディングプロトコルとしてAltitudeに注目
- パブリックローンチ後、BTCおよびETHの預入が急増し、TVL(預かり資産総額)が1,000万ドルを突破
- Altitude独自の資本効率や使いやすいユーザー体験が高評価を得ている
Altitudeとは?新しいDeFiオンチェーンレンディングプロトコルの特徴
Ethereum上に構築されたAltitudeは、分散型金融(DeFi)分野で注目を集めている新しいオンチェーンレンディングプロトコルです。
暗号資産の担保を最適化し、利用者が預けたBTCやETHといった資産を活用して効率よく利回りを得ながら、借入コストを抑えることを目指しています。プロトコルは債務と担保の管理をリアルタイムで行う点が特徴です。
AltitudeのTVLが1,000万ドル突破:BTC・ETHの預入急増
Altitudeはパブリックローンチから1か月足らずでTotal Value Locked(TVL、預かり資産総額)が1,000万ドル(約15億円超)を突破しました。これは、6月中旬に終了したプライベートベータの成功を受けたもので、ローンチ後にBTCおよびETHの預入が急増した結果です。暗号資産担保の需要増加が、急速なTVL成長につながっています。
Altitudeは担保となるBTCやETHの価格変動に応じて自動的にリバランスを行い、最適なローン価値比率(LTV)を確保します。これにより、オンチェーンでの借入効率を高めながら、担保不足(アンダーコラテラライズ)を防ぐよう設計されています。
従来のDeFiレンディングとAltitudeの違い
従来のDeFiレンディングプロトコルでは、資本効率の低さが問題視されており、LTVは30~40%に抑えられることが一般的でした。そのため、預けた資本の半分近くが未使用となっていました。
Altitudeのプロトコルでは「資本効率の最大化」と「借入プロセスの簡素化」が実現されており、ユーザーはより積極的に利回りを追求でき、さまざまなDeFiの機会を活用できるようになっています。
Altitudeのユーザー体験と安全性
Altitudeのダッシュボードは直感的で見やすく設計されています。担保価値が上昇した場合は、その増加分を利用して追加の借入や利回り戦略に活用し、ローン残高の削減も図ります。
逆に担保価値が下落した場合は、最適なLTVを維持するため、資金をレンディングプールへ再配分します。また、常に最も競争力のある貸付金利を確保し、コスト効率の高い資金調達を行っています。これにより、DeFi初心者でも安心して利用できる環境となっています。
Altitudeの資金調達と注目される背景
AltitudeはTioga Capital、New Form Capital、GSRといった著名なWeb3系ベンチャーキャピタルから610万ドルの資金調達に成功しており、その革新的なアプローチに大きな期待が寄せられています。投資家たちは、ユーザーが安全かつ効率的に利回りを最大化できる点を高く評価しています。
まとめ
AltitudeはEthereumの分散型金融領域に特化した新しいオンチェーンレンディングプロトコルとして誕生しました。
TVLが1,000万ドルを超える急成長は、BTCやETHの資産を預けるユーザーの需要の高さを裏付けています。自動リバランスやダッシュボードなど、利便性と安全性に配慮した設計が評価され、従来の資本効率問題を克服しています。
参考URL: