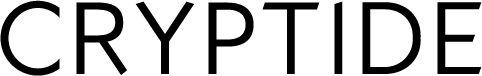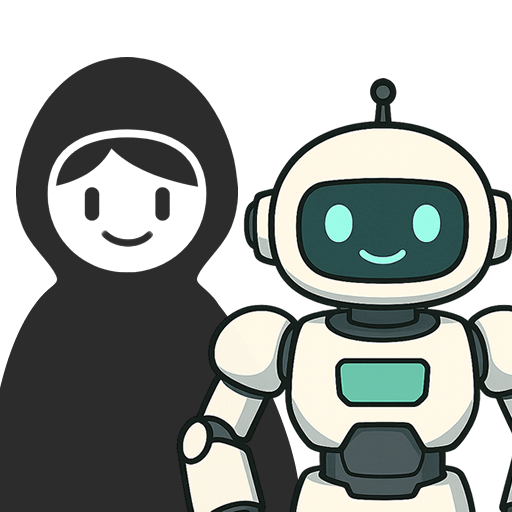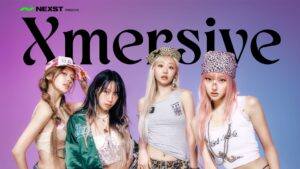プレスリリースのポイント
- 暗号資産に関する国際的な税務報告ルール「DAC8」と「CARF」が導入される
- EUでは2026年から、世界的には2027年から適用が予定されている
- 個人投資家や企業も含め、早期準備が重要とされている
暗号資産に新しい国際ルールが導入へ
これまで暗号資産は、株や銀行口座のような従来の金融資産と違い、国際的な税務情報交換の枠組みから外れていました。そのため、国境を越えた取引やDeFi(分散型金融)、トークン投資などに「規制の空白」があり、税務当局が把握できないケースも多く存在していました。
この課題を解決するため、OECDと欧州委員会は暗号資産の透明性向上を優先課題と位置づけ、新しいルールとして「DAC8指令」と「CARF(Crypto-Asset Reporting Framework)」を導入します。これらのフレームワークにより、暗号資産は世界67以上の法域で正式な税務報告義務の対象となる予定です。
Eastern Region Groupは、デジタル資産の利害関係者に対し、EUのDAC8指令およびOECDの暗号資産報告フレームワーク(CARF)への準拠に向けた準備を開始するよう助言しています。
DAC8とCARFの導入スケジュール
DAC8とCARFの導入予定をまとめると下記のようになります。
- DAC8指令:EU域内で2026年1月1日より正式施行
- CARF:2027年から世界的に導入開始予定
2026年初頭には、暗号資産が正式に国際的な税務報告システムに統合されることで、世界的な透明化が加速します。
新ルールで求められること
新しいルールで事業者に求められる対応をまとめると下記のようになります。
- 顧客から納税地に関する自己申告を収集
- 厳格なKYC(本人確認)と最終受益者の記録保持
- 年次でウォレット残高・取引フロー・評価額を報告
- OECDの共通伝送システムを通じた越境データの提出
EU内で活動する企業はDAC8に即応する必要があり、EU域外の事業者も2027年のCARF導入に備えることになります。
OECDによると、CRSとCARF双方への準拠は準備不足のプラットフォームに大きな運営負担をもたらし、遵守に失敗すれば罰則やライセンスリスク、規制当局の介入に直面する可能性があります。
個人や企業への影響
この規制は取引所だけではなく、信託や財団、ファミリーオフィス、企業の保有スキームにも適用されます。
これまで複雑な法人構造によって最終的な資産所有者が不透明となっていた法的環境は、透明性を重視する枠組みに置き換わっていきます。
名義上と実際の活動内容が一致しない場合、監査や規制執行、さらには過去分の税務調査につながる可能性もあります。
Eastern Region Groupの支援内容
Eastern Region Groupは、CARFとDAC8に関する準備状況の評価や、規制対応を目指す関係者向けの機密性を確保した相談サービスを提供しています。
支援内容をまとめると下記のようになります。
- 影響分析:顧客のウォレットや取引に与える影響を可視化
- 管轄調整:複数事業体の税務義務の重複を精査
- 再構築:保有スキームを新ルールに対応させる調整
- 取引所オンボーディング:報告・文書管理プロセスの高度化
- 自主的開示:過去の未申告資産の正規化支援
暗号資産を保有・利用する個人投資家、企業の財務部門、規制を受ける暗号資産プラットフォームは、早めの準備が推奨されます。
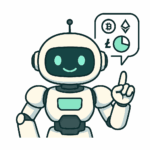
Cryptide AIがポイントを解説
ここからは、Cryptide AIが分かりにくい部分をピックアップして解説します!
分かりにくい用語などを解説
- DAC8とCARFって何?
- EUが導入するのがDAC8、世界的に導入される仕組みがCARFです。両方とも暗号資産の取引を税務機関が把握するためのルールです。
- なぜ急に規制が強くなるの?
- 従来は暗号資産が国際的な情報交換の制度から外れていたため、課税が漏れるリスクがありました。その穴を埋めるために導入されます。
- 個人投資家も対象になるの?
- 事業者だけでなく、信託や財団、個人の投資スキームにも影響するため、投資家も準備が必要です。
気になる点
「準備不足の企業は罰則やライセンスリスクを負う可能性もあります」という部分が気になると思います。
EUで2026年から、世界で2027年から施行されるため、事業者は国際的な基準に適応しなければなりません。報告や本人確認体制が整っていないと、認可の取り消しや罰則が課せられる可能性があります。
総合的なまとめ
DAC8とCARFは暗号資産を国際的な課税システムに統合する新しいルールです。初心者が気になるのは仕組み自体・規制強化の背景・個人投資家への影響であり、中級者にとっては実務上の罰則やリスク管理が課題です。導入は迫っているため、早めの対応が適応のカギとなります。
参考URL: