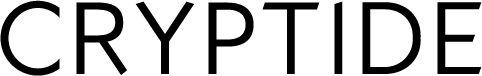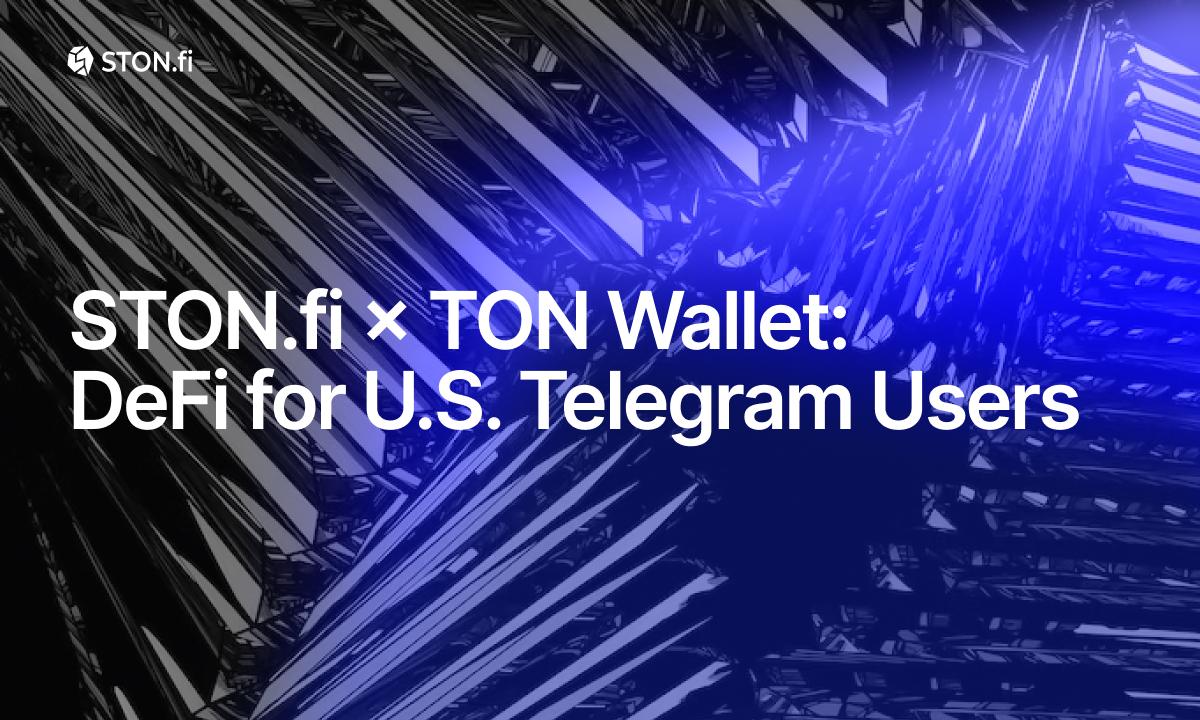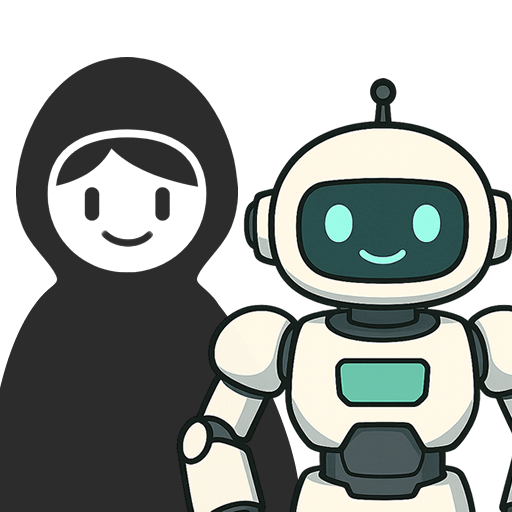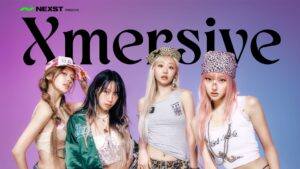プレスリリースのポイント
- STON.fiがTONエコシステムで重要なDeFiプラットフォームとして拡大
- TON Wallet連携による直感的なトークンスワップと米国Telegramユーザーへの提供開始
- 今後のクロスチェーン対応によるDeFiのグローバル展開
STON.fiとは?
STON.fi(ストン・エフアイ)は、The Open Network(TON)ブロックチェーン上に構築されている主要な分散型金融(DeFi)プラットフォームです。主にトークンスワップや流動性提供、ステーキング、イールドファーミングなど、暗号資産を簡単に運用できる仕組みを持っています。
STON.fiはTON上で唯一無二の存在感を放ち、累計取引量は60億ドル超、ユーザー数は550万人、取引件数は2,700万回以上を記録しており、ネットワーク全体のおよそ80%のトレーダーを占めています。
TON Wallet連携
STON.fiはTONブロックチェーン最大級のウォレットであるTON Walletと連携し、米国ユーザーにもスワップ機能の提供を開始しました。このウォレット連携 により、ユーザーはTON Walletのアプリ内で直接トークンスワップを行うことができ、操作も直感的です。
Telegramにネイティブ統合されたことで、操作の障壁が取り除かれ、チャットを開くのと同じくらい直感的に自己管理型DeFiを利用できるようになっています。これまでDeFi利用時の障壁だった「難しそう・操作が複雑」といった不安を解消し、より多くの人に暗号資産の活用機会を広げています。
Omnistonが実現する最適なスワップレートと分散型流動性
STON.fiのウォレットは、分散型流動性アグリゲーター「Omniston」によって支えられています。このプロトコルは複数の流動性ソースを経由することで、ユーザーが常に最適なスワップレートを受け取れるように設計されています。
さらに、Omnistonは開発者や流動性提供者にも恩恵をもたらし、統一された仕組みで最高水準のレートを一般ユーザーにも提供しています。
STON.fiの米国展開とTelegramユーザーへの新たな価値
今回、STON.fiは約8,700万人もの米国Telegramユーザー向けにスワップ機能の提供を開始しました。米国では初の展開となり、自己管理型の分散型金融へのアクセスが一気に広がることになります。
STON.fi Dev CEOのSlavik Baranov氏は、次のようにコメントしています。
「最も多く利用されているTONウォレットのひとつにスワッピングサービスを直接組み込むことで、これまで多くのユーザーがDeFiを利用する際に直面していた障壁をなくします。これにより、誰もがメッセージを送るのと同じくらい簡単に暗号資産を活用できるようになります。」
今後の展望
STON.fiは今後、クロスチェーン機能の導入を予定しています。これが実現すれば、ブリッジやラップド資産を介さずとも、複数のブロックチェーンをまたいだスワップ取引が簡単にできるようになります。
まとめ
STON.fiは、TONエコシステム内で高いユーザー数と取引実績を持つ、分散型金融プラットフォームです。
TON Walletとの連携により、直感的なトークンスワップを米国Telegramユーザーにも提供することで、より多くの人々が暗号資産を簡単に利用できる環境づくりを進めています。
参考URL: