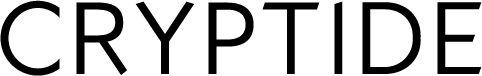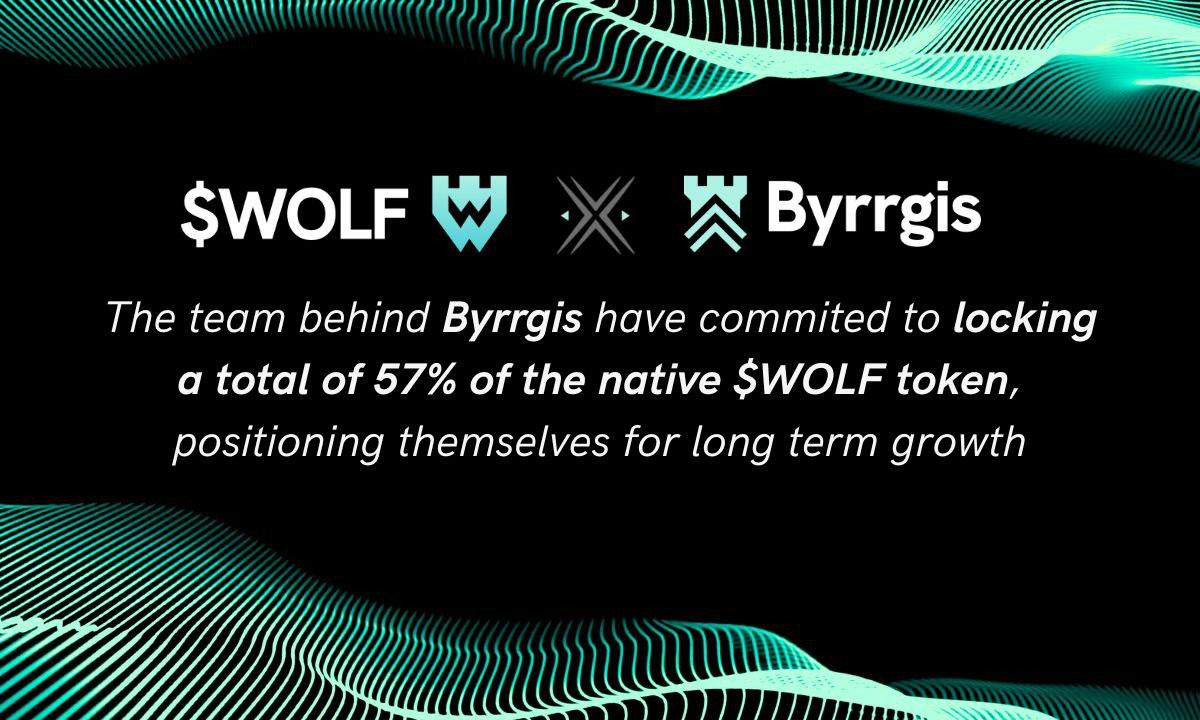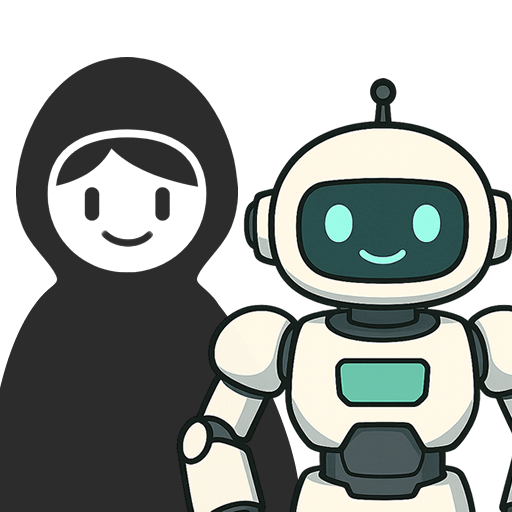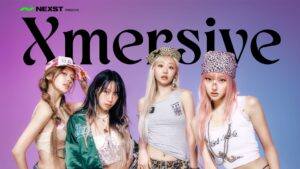プレスリリースのポイント
- WolfがWOLFトークン総供給量の57%を2年間ロックし、信頼回復を図る
- ブリッジインシデントへの迅速な対応とセキュリティ強化
- DeFi業界での透明性と説明責任を重視
WOLFトークン、総供給量の57%を2年間ロックし信頼回復へ
DeFiハブ「Wolf」は、2025年10月9日に、ブリッジインシデントへの対応として新たな施策を発表しました。
その中で最も注目を集めているのが、全WOLFトークンのうち57%以上を2年間ロックするという決定です。
この措置は、信頼回復とオンチェーンエコシステムの持続的な成長を目的としており、トークンの売り圧を抑え、保有構造やベスティング(権利確定)の透明性を高めるねらいがあります。
ブリッジインシデントの詳細とWolfの即時対応
2025年9月末、WolfはWOLFトークンに影響を与える2つの問題を経験しました。
- 外部契約者がEthereumブリッジのセットアップ時に所有権を不正に保持し、これを悪用して裏付けのないETH-WOLFを発行、約60万ドル超の資金を引き出した
- 初期の大口保有者が秘密保持契約(NDA)やコミュニティロックへの参加を拒否し、トークン総供給量の約2%を売却
いずれも現在は解決しており、インシデントの影響を最小限に抑え、再発を防ぐためにセキュリティを強化しました。
透明性と安全性を支えるStreamflowロック機構
Wolfは主要なWOLFトークン保有者全員が「Streamflow」を通じてトークンをロックし、総供給量の57%にあたる5億7,000万枚以上(約1,320万ドル分)を2年間拘束しました。
このロックは段階的に解除され、2年経過後に2.5%がベスティング。さらに再ロックも可能とされています。
トークン保有者はロック情報を誰でも確認できる仕組みとなっており、透明性が一層高まっています。
経営陣のコメント:
Byrrgis/WolfのCEOであるSiraaj Ahmed氏は、次のようにコメントしています。
「広範なホエールコミュニティが現在一致団結したことで、WOLFは今後比類のない安定性を手に入れました。ETHブリッジのインシデントを解決するために取られた断固たる対応と相まって、私たちはDeFiにおける透明性と説明責任の新たなベンチマークを打ち立てようとしています。Byrrgisの下で、この基盤はWeb3エコシステムがどう構築されるべきか――長期的で、透明性が高く、信頼を最小化した形――の青写真となるでしょう。」
また、CTOのRobert Freeman氏は次のようにコメントしています。
「ETHブリッジは完全に監査されていたにもかかわらず、残念ながら管理者権限を乱用した契約業者によってアクセスされました。私たちは即座に対応し、ブリッジを停止してフォレンジック調査を開始しました。この経験から学んだことが、今ではより高い基準を形成しています。WOLFは全てのサービスとインフラにおいて、最小権限アクセスとオンデマンド権限昇格を備えたゼロトラストセキュリティ原則を適用しています。」
さらに、CMOのAmy Cooksey氏は次のようにコメントしています。
「WolfがStreamflow上で供給量の半分を保護し、より厳格なベンダー管理と監査を導入した対応は、Byrrgisエコシステム全体で実施される基準を示すものです。私たちのビジョンは、あらゆる層でのレジリエンス――コミュニティが整合性を確認し、約束を追跡し、システムが個々のアクターよりも強固であると信頼できる状態――を実現することです。これこそがByrrgisの差別化要因です。課題を回避するのではなく、正面から立ち向かい、より強く成長することで違いを生み出しているのです。」
Byrrgisとは
Byrrgisは、透明性・自動化・プロフェッショナル向けツールを融合させたDeFiハブで、WOLFトークンを基盤としたユーティリティプラットフォームを展開しています。
- マルチチェーン・パック機能による効率的な資金運用
- 資本を自動で最適化し、トレーダーが戦略的に活用できる
- 「説明責任・透明性・回復力」を強化するための仕組み
これらの技術により、ByrrgisはDeFi分野で最も高度なポートフォリオプラットフォームの一つとなっています。
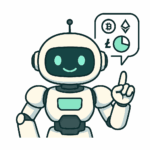
Cryptide AIがポイントを解説
ここからは、Cryptide AIが分かりにくい部分をピックアップして解説します!
分かりにくい用語などを解説
- トークンロックとは?
- 開発チームや大口保有者が保有するトークンを一定期間使えないようにする仕組み。価格の急変を防ぎ、安心感を与える目的がある。
- ゼロトラストとは?
- システム内外を問わず、すべてのアクセスを検証する考え方。権限を最小限にして不正アクセスを防ぐセキュリティ手法。
- ベスティングとは?
- トークンや報酬が段階的に受け取れる仕組み。プロジェクトの長期的な安定性を支えるために重要。
気になる点をピックアップ解説
「トークンをロックすると信頼回復につながるのか?」という部分をピックアップ解説します。
トークンをロックすることで、運営側が自由に売却できないため、市場の信頼を高めます。これは開発側の誠実な意思表示であり、投機的な動きを抑える効果があるため、結果的に信頼の回復につながります。
総合的なまとめ
Wolfが実施したトークンロックと透明性の高い運用体制は、ブリッジインシデントを乗り越えるための重要な再生策となり、DeFi業界における「信頼構築の新モデルケース」として注目を集めています。 Byrrgisグループも透明性と説明責任を中核に据えた体制を整備しており、今後の展開が期待されます。
参考URL: